

お盆は新のお盆と旧のお盆があります。その違いを分かりやすく説明しております。迎え火とは?送り火とは?も詳しく解説。
お盆いつ?新のお盆と旧のお盆
お盆の時期について
お盆はもともと旧暦の7月13日〜16日に営まれていました。
しかし、明治5年に新暦(現在の暦)が導入されたことで、旧暦との間に約1か月のずれが生じ、現在では地域によって「新のお盆」と「旧のお盆」の二つの時期が存在しています。
新のお盆:新暦の7月13日〜16日
(主に関東地方など)
旧のお盆:新暦の8月13日〜16日
(主に関西地方など)
どちらの時期を選んでも構いません。ご先祖さまを偲び、心静かに手を合わせていただける日を、ご家庭のご都合に合わせてお選びください。
浄土真宗におけるお盆の考え方

【ポイント】
浄土真宗では、お盆の時期に特別な仏壇飾り(ナスビやキュウリの精霊馬など)を設ける必要はございません。
通常の法要と同様に、お仏壇にお花やお供え物をお供えし、仏さまへのご報恩とご先祖への感謝の気持ちでお参りいただければ結構です。
また、提灯なども必須ではありませんが、お仏壇の横にそっと灯す提灯の明かりは、心を癒してくれるものでもあります。
各ご家庭のご事情に応じて、無理のない範囲でご準備いただければと思います。
迎え火とは
新暦のお盆では7月13日、旧暦のお盆では8月13日に行われる行事で、ご先祖様をお迎えすると言われています。

地域によっては家の門口や玄関先で火を焚き、その明かりを目印にご先祖様が迷わず帰ってこられるよう願います。
しかし、浄土真宗では「亡き方は命終ののち、阿弥陀如来のお浄土に往生される」といただくため、霊が一時的に帰ってくるという考え方はいたしません。
そのため、迎え火の風習は行わず、代わりに仏前にお花やお供えを整え、お念仏と感謝の心でお迎えします。
送り火とは
新暦のお盆では7月16日、旧暦のお盆では8月16日に行われる行事で、お盆にお迎えしたご先祖様を再び送り出す意味があるとされます。

多くの地域では迎え火と同じく火を焚き、その灯りでお見送りする風習があります。
浄土真宗では送り火も行わず、「亡き方はすでに阿弥陀さまの浄土において仏となられている」という教えに基づきます。
お盆の終わりには、お念仏を称えて感謝の気持ちを深め、これからも仏法をよりどころに日々を歩ませていただく決意を新たにし、お念仏と感謝の心でお見送りします。
FAQ形式 要点まとめ
浄土真宗でも、お盆に法要をする意味はありますか?-
はい、深い意味があります。
浄土真宗では「ご先祖がこの世に戻ってくるから迎える」という考えはとりませんが、お盆は仏さまのご縁をいただき、ご先祖への感謝を思い起こす大切な時間です。
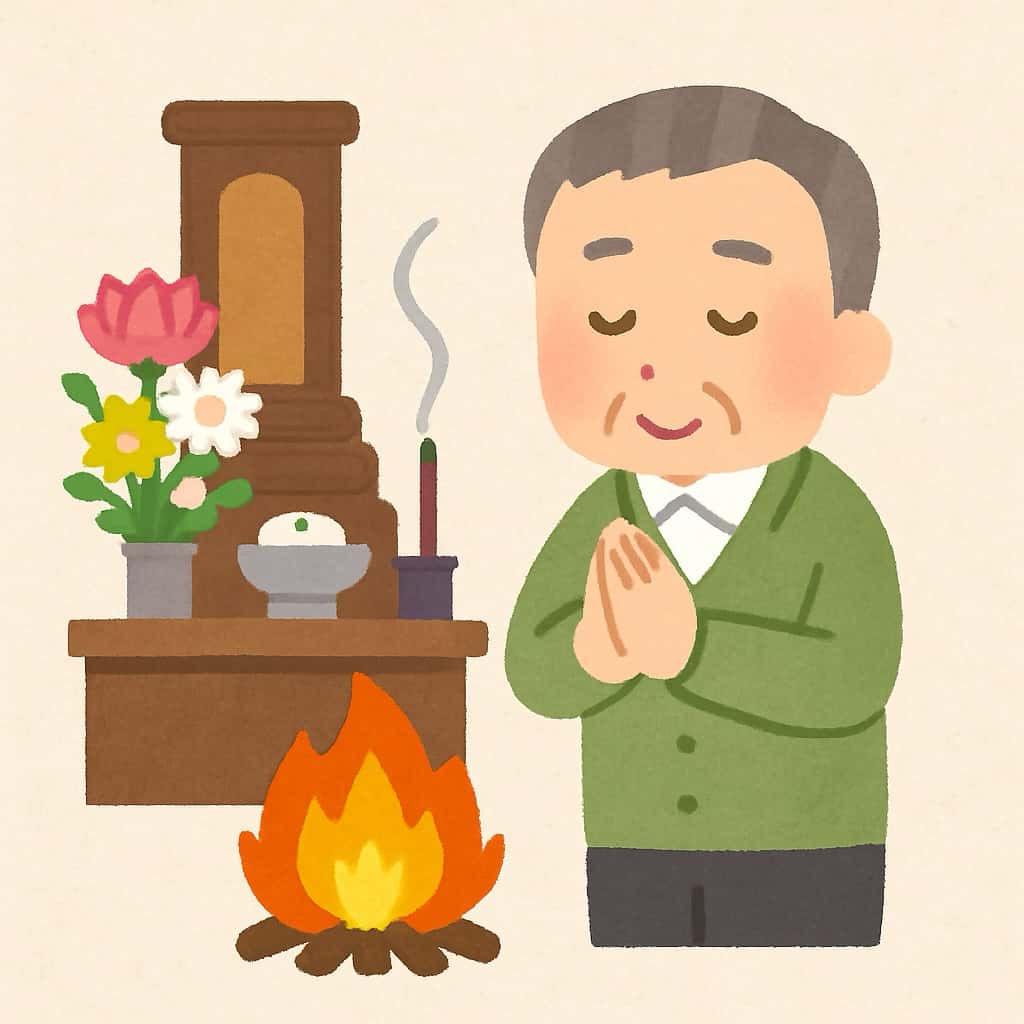
法要は“亡き人のためだけ”ではなく、いまを生きる私自身が、いのちのつながりと仏さまのはたらきに気づく場として営まれます。
迎え火・送り火は浄土真宗では行わない方が良いですか?-
してもしなくても構いません。大切なのは「心」です。
迎え火や送り火は、ご先祖を偲び、その存在を思い出す民間の風習として大切にされてきました。
浄土真宗では「火を焚かなければ帰れないご先祖がいる」とは考えませんが、火を見つめながら手を合わせる“感謝の心”そのものは尊いものです。

仏壇にお花やお供えを整え、お念仏を申すことが何よりの供養となります。
盂蘭盆経と“お盆=ご先祖が帰ってくる”という考え方はどう関係しているのですか?-
目連尊者のお母さんの物語から、供養の心が広まりました。
盂蘭盆経では、目連尊者が母を想い、僧侶への供養を通じて救いを得たと説かれています。
この教えは、「親やご先祖を思う心の尊さ」「感謝の行いが福となる」ことを伝えるものです。

後の時代に民間の信仰と結びつき、“ご先祖が帰ってくる日”という形で広がりましたが、本質は「感謝と報恩のこころ」にあります。
精霊馬(ナスやキュウリ)・提灯・迎え火などは準備しないといけませんか?-
必須ではありません。形よりも「念ずる心」を大切にします。
浄土真宗では、精霊馬や特別な飾りは義務ではなく、準備しなくても失礼には当たりません。
家族で仏壇を整え、花を供え、静かに手を合わせるその時間こそが、何より尊いご供養です。

また、ナスやきゅうりの精霊馬も、「霊の乗り物」と捉えるのではなく、お盆の雰囲気を感じ、ご先祖やいのちを思い出す“しるし”として飾られるのであれば、心のこもった大切な表現として受けとめられます。
仏さまとのご縁、人と人とのご縁。そのあたたかなつながりを、真心を込めて大切にいたします。
