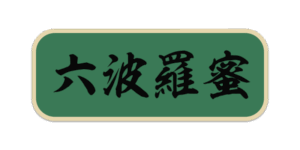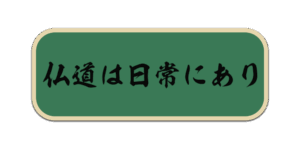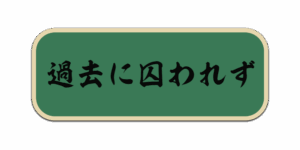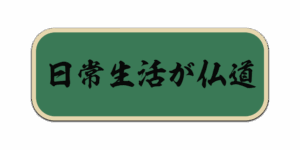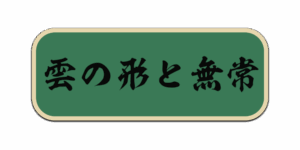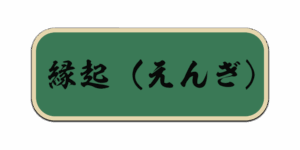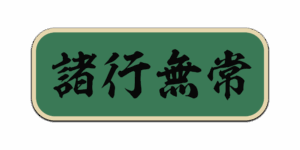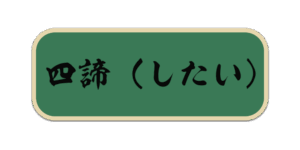言葉は頭で理解するものですが、実践は心で感じ取るもの。そこに初めて法話としての力が宿ります。
仏教用語の説明は法話ではない
法話というのは、単に仏教用語の意味を説明するものではありません。本来の法話は、聞く人の生活の中で活かされてこそ、仏様の教えが息づくのです。たとえば「自他不二」という言葉ひとつをとっても、ただ「自分と他人は一つです」と言葉で解説するだけでは、心に届きにくいものです。
しかし、それを実生活に置き換えて語ると意味が変わってきます。人の喜びを自分の喜びと感じること、他人の悲しみを共に担おうとする姿勢。そうした日常の場面を通じて「自他不二」が具体的に見えてきます。言葉は頭で理解するものですが、実践は心で感じ取るもの。そこに初めて法話としての力が宿ります。
仏教は「聞いて知る」だけで終わるものではなく、「生きて実践する」ことで輝きを増す教えです。阿弥陀仏の慈悲に照らされ、私たちは自分を知り、他者を思いやりながら生きる道を歩むことができます。法話はその道しるべであり、聞く人が自分の生活に結びつけたときにこそ、真の意味を持つのです。
だからこそ、法話は言葉の知識を語るだけでなく、生活に根差し、心を動かすものでなければなりません。仏様の教えを実践に移す一歩を踏み出したとき、私たちの心に本当の安らぎが訪れるのです。
言葉を知った覚えたでご供養になりますか?法要は供養であって学問ではありません。私たちの心の実践が大切なのです。合掌🙏
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
このお話は入仏式のご縁でもお伝えすることがあります。新しい仏壇を迎える際には「入仏慶讃法要」を営みます。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。