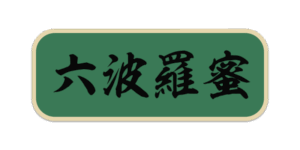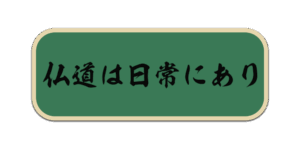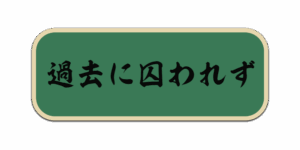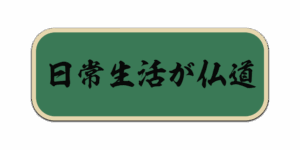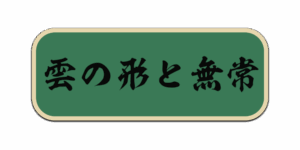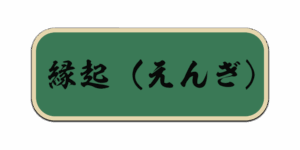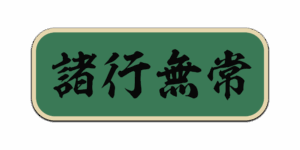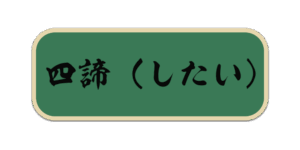十分な休息をとり、心に余裕があるときは、自然と他者にも温かく接することができます。
自利利他(じりりた)とは
私たちは日々、さまざまな人と関わりながら生きています。家族、友人、仕事仲間、そして初めて出会う人々。その中で「他者を大切にすることは大事だ」と多くの人が考えますが、実はその前提として「自分を大切にすること」が欠かせません。仏教では「自利利他(じりりた)」という教えがあります。これは、「自らの心を整え、満たすことで、他者をも助けることができる」という意味です。
心が疲れ切っていたり、自己否定の気持ちが強かったりすると、他者への思いやりも自然と薄れてしまいます。反対に、心が穏やかで安定していると、相手の言葉に耳を傾け、優しく接することができるのです。例えば、忙しさに追われて自分の時間を持てないとき、ついイライラして家族や周りの人に冷たく接してしまうことはないでしょうか?逆に、十分な休息をとり、心に余裕があるときは、自然と他者にも温かく接することができます。
また、「自分を愛すること」と聞くと、自己中心的なことのように感じる人もいるかもしれません。しかし、ここで言う「自分を大切にする」とは、怠惰に流されることではなく、自分の心と体を健やかに保ち、正しく生きることを指します。無理をせず、自分を責めすぎず、けれども怠らずに日々を過ごすこと。それが、自分自身への本当の優しさなのです。
自分の心を整えることは、他者を思いやる第一歩です。仏教では「和顔愛語(わげんあいご)」という言葉があります。これは、「和やかな表情と優しい言葉で人と接する」という意味ですが、それは決して無理に作るものではなく、心が安らいでいるからこそ自然と生まれるものです。まずは、自分自身を慈しみ、穏やかな気持ちで生きること。それが、周囲の人々にも温かさを広げていく道なのです。合掌🙏
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
この法話は四十九日法要のご縁でもお伝えすることがあります。ご供養の中でも特に重んじられるのが49日です。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。