49日法要までの数え方

四十九日法要はいつ?

四十九日法要は、故人様が迷いの世界を離れ、仏のもとへと導かれる大切な節目の日です。亡くなってから七日ごとに行われる法要の中でも、七回目にあたるこの日を満中陰(まんちゅういん)とも呼び、忌明け(きあけ)を迎える日とされています。この日をもって喪が明け、ご遺族は少しずつ日常生活へと心を向けていく時期にもなります。
ただし、「四十九日」は暦の49日後とは異なり、仏教の教えでは亡くなった日を一日目として数える「数え日(かぞえび)」で計算します。
そのため、日取りを決める際には注意が必要です。地域や宗派によって多少の違いがあるため、正確な日にちを確認した上でご予定を立てると安心です。
次に、実際の「49日までの数え方・計算方法」について詳しく見ていきましょう。
49日までの数え方・計算について
四十九日法要の日取りを決める際には、亡くなられた日を「一日目(初日)」として数えます。
これは仏教の数え方で、亡くなった当日を含めて日数を数える「数え日」という考え方です。
つまり、亡くなった日から数えて7日目が初七日、49日目が四十九日法要(満中陰)となり、この日が忌明けの節目となります。

(例)8日に亡くなった場合は14日が初七日になります。
亡くなった日(8日)から数えます。
この数え方は、一般的な暦の感覚とは少し異なるため、法要の計算をするときは注意が必要です。
四十九日法要の日をお調べ致します。(料金はかかりませんのでご安心下さい)
但し、来て頂くお坊さんが決まっている場合や、お寺とのお付き合いのある方はご遠慮願います。また、番号非通知も不可です。
●お葬式の時に中陰表を頂けなかった ●お葬式の時にお寺を呼ばなかった。など、このような場合はいつでもお電話でご質問下さいませ。
中陰表についてはこちら
四十九日法要のことをネットでお調べしても、なかなか思い通りの検索結果が出てこないことが多々御座います。
そのような場合は、一人で悩まずにいつでもご質問下さいませ。


お坊さん@出張®︎では経験豊富な現役僧侶がお答え致しますので現実的で確実なご返答が出来ます。
よくいただくご質問には、次のようなものがあります。
- ○月○日に亡くなった故人の、49日の日を教えて下さい。
- 49日法要の準備にはどんなものが必要ですか?
- 法要を行う時間は午前と午後のどちらが良いですか?
などのご質問が多いようです。
下記にFAQとして詳しい回答をご用意しております。ぜひご参考になさってください。
FAQ形式 要点まとめ
- ○月○日に亡くなったのですが、四十九日法要はいつになりますか?
-
亡くなられた日を「一日目(初日)」として数えて計算して下さい。
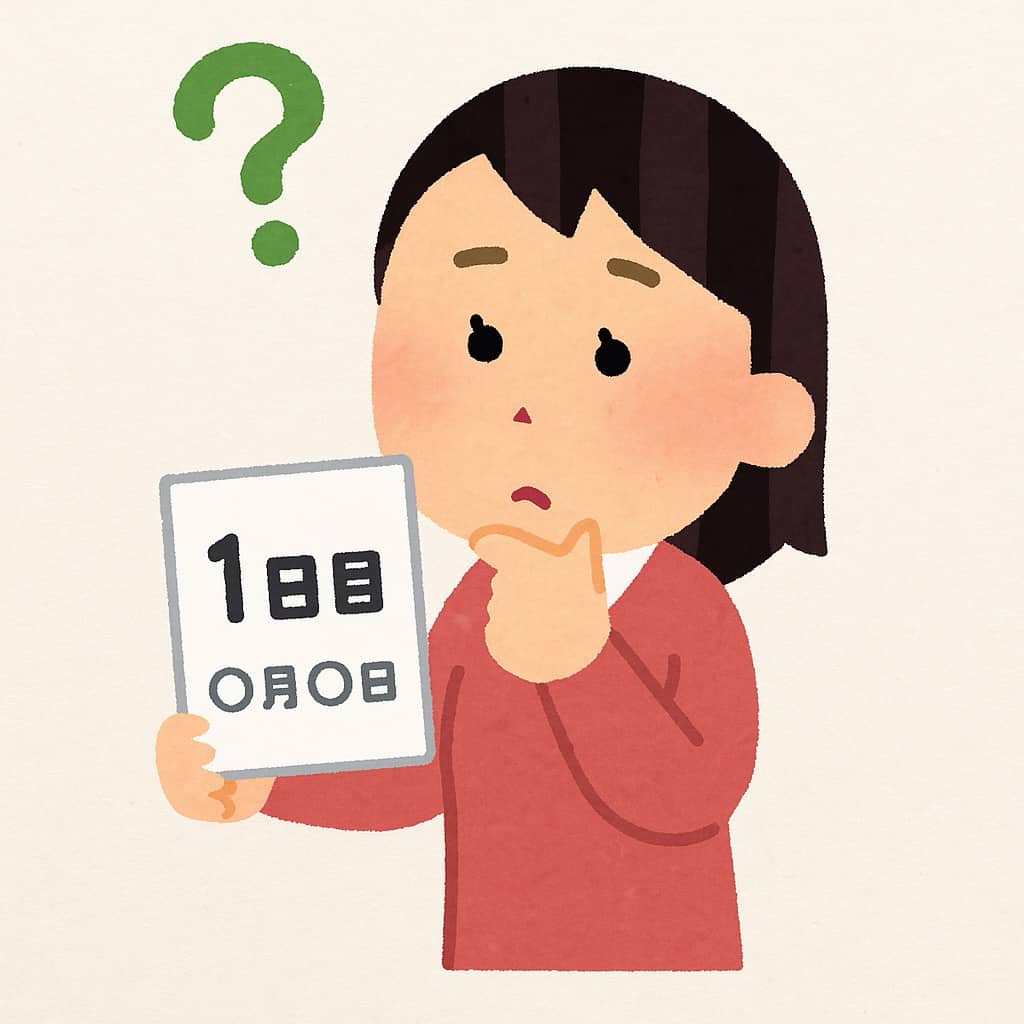
- 四十九日法要には何が必要なのですか?準備するものを教えて下さい。
-
49日法要に必要なものは、49日の準備リストをご参考になさって下さい。
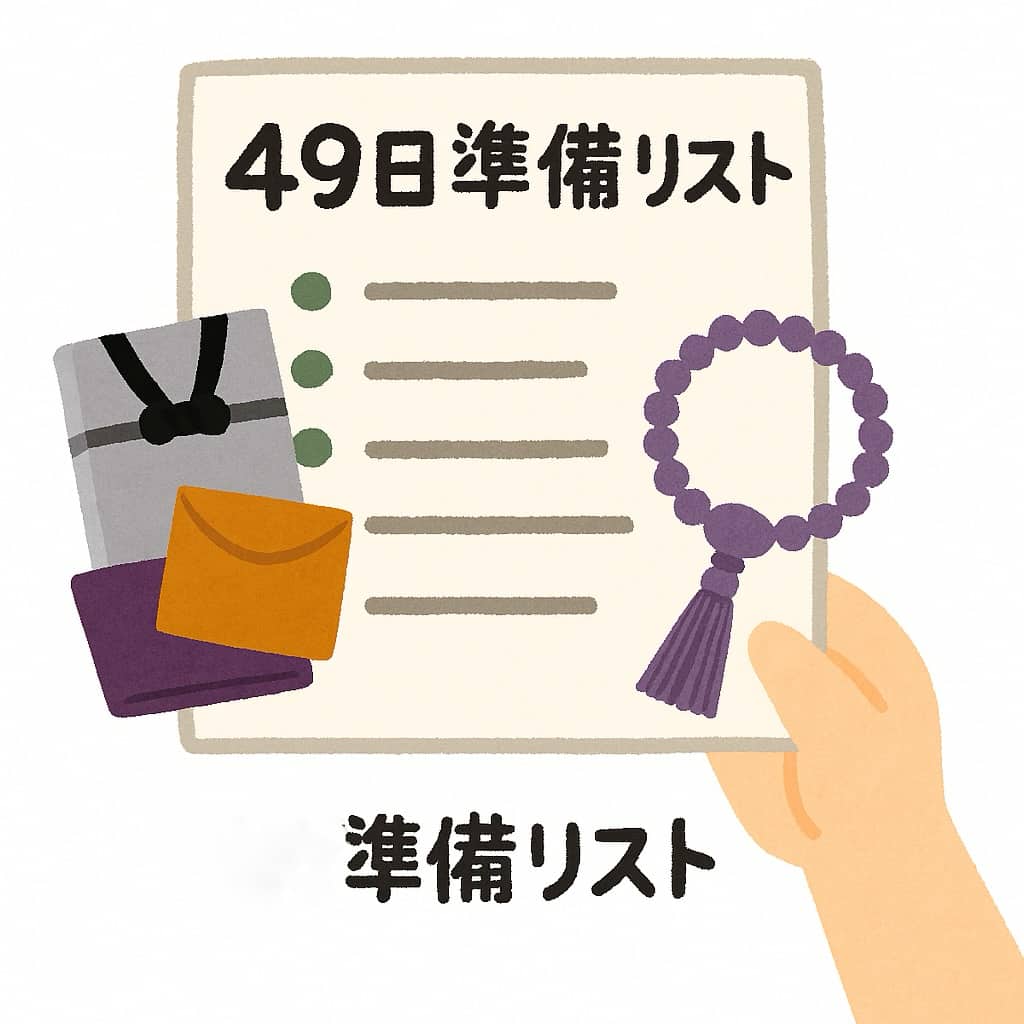
- 四十九日法要は午前か午後か、法要を行う時間は決まっているのですか?
-
49日法要を行う時間は決まっておりません。どちらでも大丈夫です。

午前・午後・ご希望の時間帯に合わせてお伺いします。ご家族のご都合を優先してお考えください。

四十九日法要は、数ある法要の中でも一番大切にされる法要ですので、静寂で素晴らしい法要ができるよう、しっかりと準備したいですね。
お問合せ・ご相談・対応地域

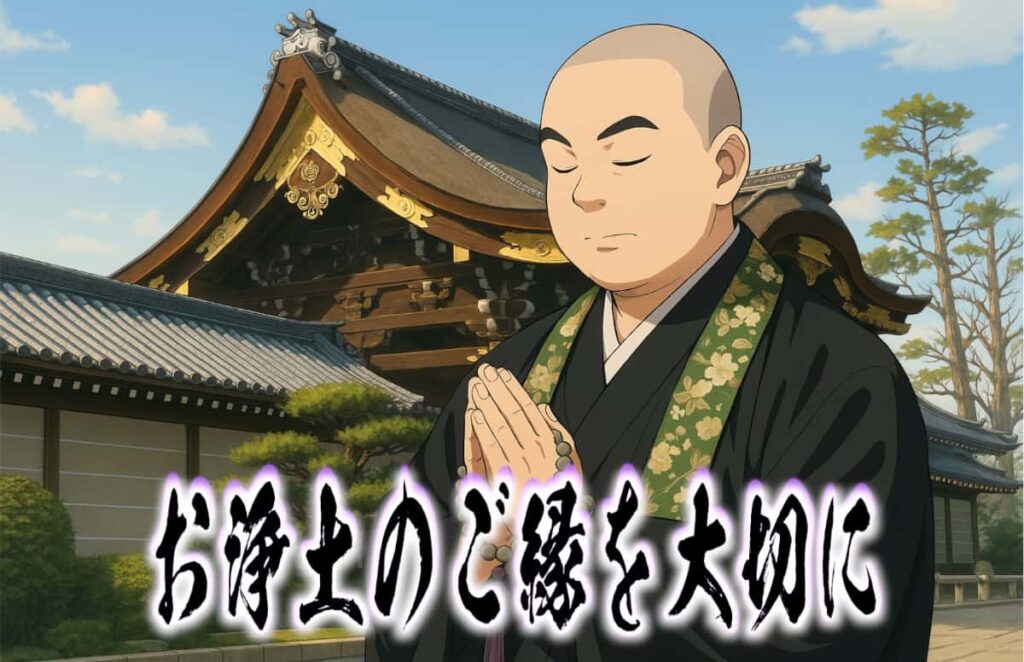
丁寧にご供養いたします。
※法要中などでお電話に出られない場合でも、携帯番号【070-2300-7888】から折り返しご連絡いたします。
📞受付時間(9:00〜17:00)
受付時間外はメールやLINEでお願いします。
※営業・勧誘目的のご連絡は固くお断りしております。


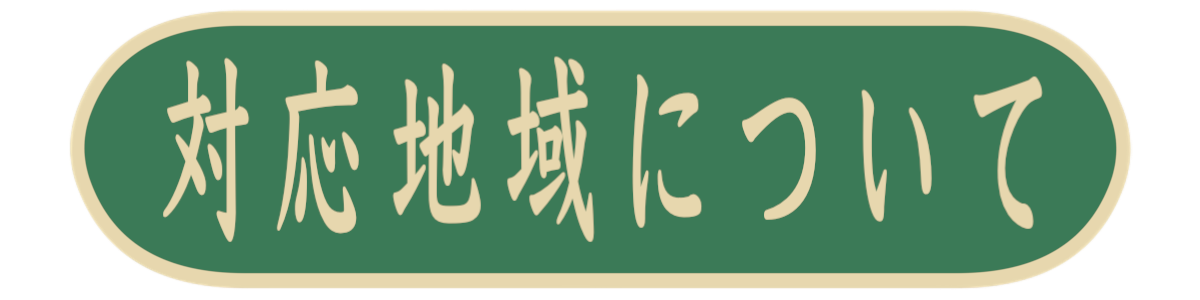
大阪・京都・兵庫・奈良を中心に、関西全域で法要・ご供養を承っております。

スムーズなお返事のために
メールやLINEを送信いただいた際、半日以上経っても返信がない場合は、こちらに届いていない可能性がございます。
その場合は、お手数をおかけしますが、お電話にてご連絡をお願い申し上げます。また、お急ぎの際はお電話でのご連絡を最優先にお願いいたします。
法要中などでお電話に出られない場合もございますが、一時間以内には必ず折り返しのお電話を差し上げております。
何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。合掌🙏







