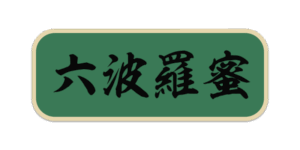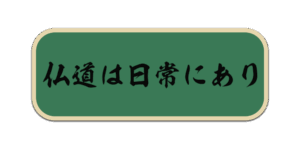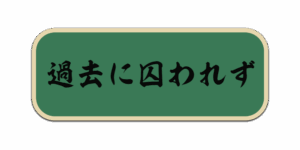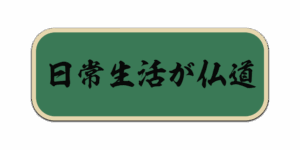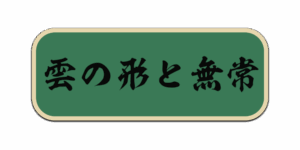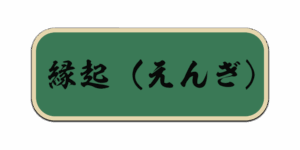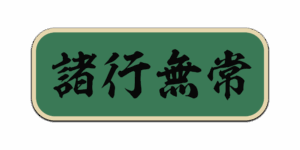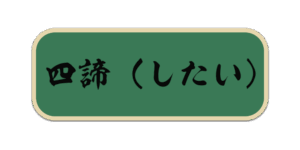大切なのは、日々の生活の中で心をどのように保ち、煩悩に振り回されずに生きるかということです。
慈悲と智慧をもって人と接する
仏教では、悟りとは特定の環境や立場によって決まるものではなく、心の在り方によって得られるものとされています。出家者であれ在家者であれ、仏法に生き、煩悩を超えて真理に目覚めることができれば、それが悟りの境地です。
お釈迦様の時代、多くの弟子たちは出家して修行に励みましたが、中には在家のまま悟りを開いた者もいました。たとえば、ヴィサーカーという女性信者は、在家の身でありながら深い信仰と智慧を持ち、多くの功徳を積んだことで知られています。また、スダッタ長者(給孤独長者)も、在家のままで仏教の教えを深く理解し、実践しました。
出家は確かに修行に適した環境を整えやすいですが、それだけが悟りへの道ではありません。大切なのは、日々の生活の中で心をどのように保ち、煩悩に振り回されずに生きるかということです。たとえ俗世にあっても、正しい道を歩み、慈悲と智慧をもって人と接するならば、それは出家の修行と同じく尊いものとなります。
私たちは皆、それぞれの人生の中で仏道を歩むことができます。大切なのは、自分の置かれた場所で最善を尽くし、心を磨くこと。悟りとは遠い世界の話ではなく、日常の中にこそあるのです。
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
このお話は、四十九日法要でもお話することがあります。ご供養の中でも特に重んじられるのが49日です。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。