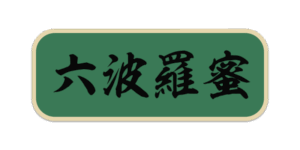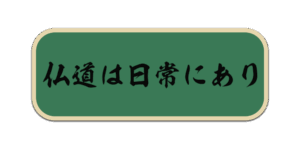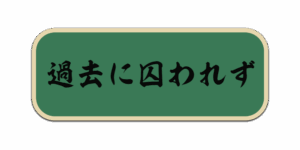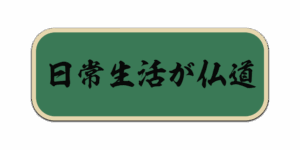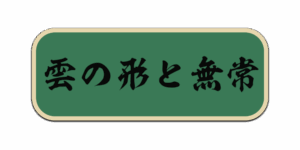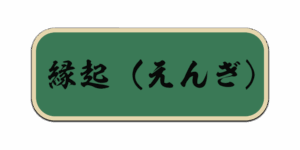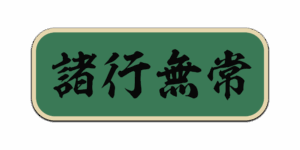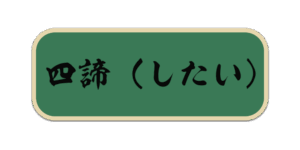病気や困難な経験をただ嘆くだけでなく、それを慈悲の種とすることが大切です。
共に悲しみ寄り添う心
私たちは健康であるとき、病や障がいを持つ人の苦しみを想像することが難しいものです。しかし、いざ自分が病を患い、不自由な状況に置かれたとき、その苦しみがどれほど大きいものかを初めて実感します。仏教には同苦(どうく)という考えがあります。これは、自分が苦しみを経験することで他者の痛みを理解し、共に悲しみ、寄り添う心が生まれるというものです。
例えば、普段は当たり前に歩いていた人が、突然病に倒れ、車椅子での生活を余儀なくされるとします。そのとき、ほんの数メートルの移動がどれほど大変か、段差がどれほどの障害になるかを初めて知るでしょう。そして、それまで気にも留めなかったバリアフリーの大切さや、サポートの必要性に気づきます。この経験を通じて、同じように不自由を抱える人々の気持ちが理解でき、自然と優しさや思いやりが生まれるのです。
仏教では慈悲(じひ)の心を大切にします。慈悲とは、他者の苦しみを取り除き、幸せを願うこと。しかし、私たちは他者の苦しみを完全に理解することはできません。それでも、自らの苦しみを通して少しでもその痛みを知ることができれば、そこに本当の慈悲が芽生えるのです。病気や困難な経験をただ嘆くだけでなく、それを慈悲の種とすることで、自分も周囲の人々も救われていくのです。合掌🙏
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
この法話は百箇日法要のご縁でもお伝えすることがあります。故人を偲び、節目ごとにご縁を確かめるのが百か日です。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。
信頼できる僧侶へのご依頼はこちらから