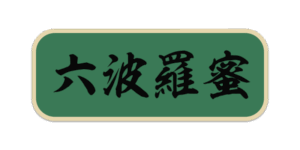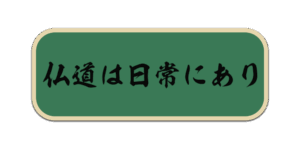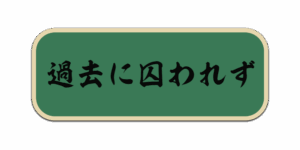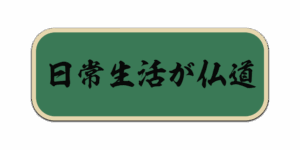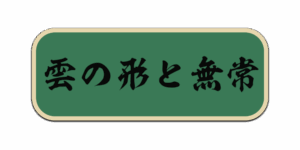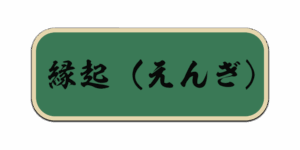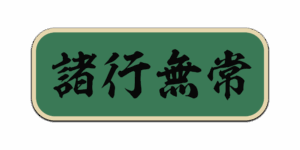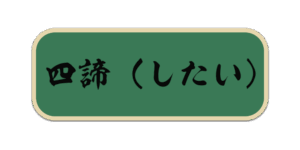無我を生きることは簡単ではありませんが、その実践を通じて、心は軽く、明るくなります。
固定不変なものは存在しない
「無我」とは、私たちが抱きがちな「自分」という固定観念から解き放たれることを意味します。仏教では、この「自分」という執着が苦しみの根源であると説かれています。私たちは、自分の成功や欲望、他者との比較に心を奪われ、それが原因で心が濁ることがあります。執着はやがて不満や不安を生み出し、私たちの心に重くのしかかるのです。
しかし、「無我」の心を実践することで、その執着から自由になり、心は澄み渡ります。無我の心で生きるとは、「私」という枠を越えて、他者や世界と調和し、共に生きるという姿勢です。それは、相手の気持ちを尊重し、与える喜びを知ることでもあります。自分の欲望を優先するのではなく、他者と分かち合うことで、心には真の安らぎと感謝が芽生えます。
仏教の教えでは、「無我」は単なる個人の心のあり方にとどまりません。私たちが「無我」の心で行動すれば、自然と周囲との関係性も調和し、互いの幸せを育むことができます。たとえば、困っている人に手を差し伸べたり、自分の利益を少し手放してでも他者のために尽くすとき、その行動が自分自身の心の清らかさを生むのです。これは「慈悲」の実践ともいえます。
『般若心経』には「空」の教えが説かれています。そこでは、すべてのものが固定された実体を持たないとされ、私たちはその空の性質の中で互いに繋がり、支え合っています。この教えを実践するためにも、「無我」の心を日々意識することが大切です。自分を空にすることで、他者の存在を受け入れ、すべてのものと調和した生き方を実現することができます。
無我を生きることは簡単ではありませんが、その実践を通じて、心は軽く、明るくなります。それは、他者と共に歩む喜びを知り、仏の教えに基づいて安らぎを得る道でもあります。今日から少しずつ、無我の心で他者と関わり、清らかな心を育ててみましょう。
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
こうした教えを実践すると、供養やお参りの意味もより深く感じられます。詳しくは[年忌法要ページ]でも解説しています。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。
出張お坊さんをお探しなら、安心の浄土真宗本願寺派僧侶へ。