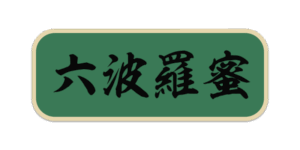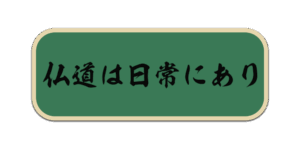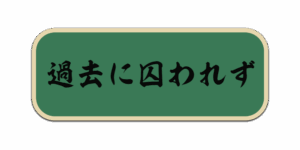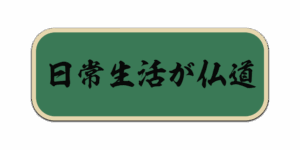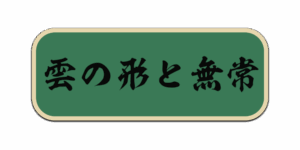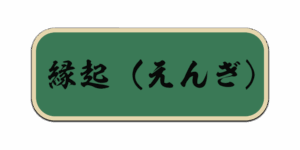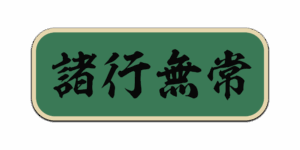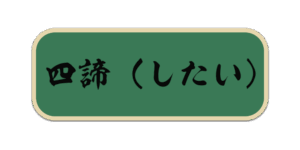善行は、その大小ではなく、純粋な心から生まれることが重要です。
布施の心は連鎖する宝物
仏教で説かれる「布施(ふせ)」の教えは、ただ物を与えることに限らず、心そのものを他者に差し向ける行為全般を指します。布施には「財施(ざいせ)」「法施(ほうせ)」「無畏施(むいせ)」の三種類があります。財施は物やお金を与えること、法施は教えを分かち合うこと、無畏施は他人の不安や恐怖を取り除くことを意味します。どれも、大きな犠牲を伴うものではなく、日常生活の中で簡単に実践できるものばかりです。
例えば、道端のゴミを拾う行為は、財施に通じます。人に優しい言葉をかけたり、微笑みかけたりすることは法施となり、困っている人に手を差し伸べる行動は無畏施の一種です。どれもささやかな行為に見えますが、その積み重ねが大きな影響を及ぼします。まるで静かな湖面に石を投げたときに波紋が広がるように、あなたの善行も周囲に温かさを伝え、さらにその先へと広がっていきます。
善行は、その大小ではなく、純粋な心から生まれることが重要です。「自分の行いは小さすぎて意味がない」と思う必要はありません。たとえ見返りがなくても、自らの中に幸せや満足感が生まれるのが布施の真髄です。これは「自利利他(じりりた)」、つまり自分と他人を共に救うという仏教の基本的な教えともつながっています。
布施を実践するとき、大切なのは「無執着(むしゅうじゃく)」の心です。見返りを求めず、自然に行う善行こそが、やがて大きな幸せをもたらします。行いの結果は目に見えないかもしれませんが、仏教では因果の法則によって必ず良い結果が生まれると説かれています。善い種を蒔けば、必ず善い果実が実るのです。
日々の生活の中で、自分ができる小さな善行を見つけてみてください。それが他者の心を温かくし、やがて自分の心も豊かにしていくでしょう。その小さな行いが、周囲に波紋を広げ、大きな幸せの流れをつくるのです。合掌🙏
「この記事は、浄土真宗本願寺派 龍眞院『お坊さん@出張®』がお届けしました。」
ご先祖様を供養する年忌法要の進め方は[年忌法要ページ]をご参照ください。
年回忌法要早見表をご覧いただくと、今年のご法要日程がすぐに分かります。